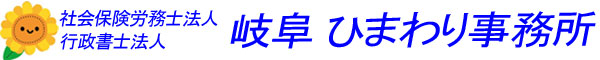顧問先事業主様からの質問
1ヶ月単位の変形労働時間制とは何ですか? また1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方は?
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、労働時間を1日単位ではなく、月単位で計算することで、繁忙期等により勤務時間が増加しても時間外労働としての取扱いを不要(残業代を支払わなくても良い場合もある)とする労働時間制度です。
しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すると、残業代の計算方法が大変煩雑になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、会社にとっても従業員にとっても、効率的な労働環境を構築することのできる、大変便利な制度ですので、ぜひ活用したいものです。
そこで今回は、
- 1ヶ月単位の変形労働時間制とは何か?
- どうすれば1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるか?
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合の残業代の計算の仕方は?
についてご説明します。

1.1ヶ月単位の変形労働時間制とは何か?
法律で定められている労働時間があります。これを法定労働時間と言います。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間と定められています。
法定労働時間と似た言葉で、会社毎にが定めている労働時間があります。これを所定労働時間と言います。
所定労働時間は、法定労働時間以下にする必要があります。
もちろん、法定労働時間を超えて働かせても良いのですが、その時間は時間外労働(残業)になります。
しかし、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用すると、ある期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間以下になっていれば、特定の日または特定の週において、法定労働時間を超えて所定労働時間を設定できることになります。
例えば、とある会社の所定労働時間を
1週目の労働時間を、1日10時間で週5日間労働、
2週目の労働時間を、1日6時間×週5日間労働
3週目の労働時間を、1日8時間×週5日間労働
4週目の労働時間を、1日8時間×週5日間労働とした場合、
1週目は、1日10時間労働ですから1日の法定労働時間を超えていますし、また 週50時間労働ですから週の法定労働時間を超えていますので、本来ならば違法ですし、時間外労働手当(残業代)の支払いが必要になります。
しかし、1週目から4週目までの平均では、週40時間となり、法定労働時間以内になっています。
もしこの会社が、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用をしていれば、違法にはなりませんし、残業代も発生しないことになります。
このように、1ヶ月以内の間で、忙しい時期と暇な時期があるような会社だと、この 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用することで、余計な時間外労働をさせる必要がなくなり残業代も支払わなくても良くなります。

2.どうすれば1ヵ月単位の変形労働時間制を導入することができるか?
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、「就業規則」又は「労使協定」によって、下記の事項を定める必要があります。
- 1ヶ月以内の一定期間(※1 変形期間と言います)を平均して週の労働時間が法定労働時間を超えない範囲(※2 労働時間の総枠と言います)で、「※3 各日、各週の労働時間」を具体的に定めること
- 労使協定による場合は、有効期間の定めをすること
なお、この労使協定は、労働基準監督署への届出義務があります。
1.「※1 変形期間」とは
1ヶ月以内の一定期間を変形期間と呼んでいますが、1ヶ月単位の変形労働時間制は、「1ヵ月」と名前がついていますが、必ず変形期間を1箇月にしなければならないわけではありません。
最長で1箇月ということです。ですので、4週間単位や2週間単位で採用しても構わないことになります。
この変形期間を平均して1週間の所定労働時間が法定労働時間を超えないように設計すれば良いのです。
ただ、必ず、「就業規則」又は「労使協定」で、その起算日を明記しておく必要があります。
(例えば、変形期間を1ヶ月とするならば「毎月1日を起算日とする」という形で明記します)
採用している多くの会社が1ヶ月(暦日数)で変形期間を設けています。
2.「※2 労働時間の総枠」とは
1ヶ月単位の変形労働時間制は、変形期間を平均して1週間の所定労働時間が法定労働時間を超えないようにする必要がありますが、この変形期間内の合計した法定労働時間を労働時間の総枠と呼んでいます。
たとえば、変形期間を1ヵ月とした場合の労働時間の総枠は、
31日の月の場合=労働時間の総枠177.1時間
30日の月の場合=労働時間の総枠171.4時間
29日の月の場合=労働時間の総枠165.7時間
28日の月の場合=労働時間の総枠160時間
となります。
すなわち、暦の月によって労働時間の総枠は違い、労働時間の総枠の範囲内で所定労働時間を定める必要があります。
3.「※3 各日、各週の労働時間」とは
1ヶ月単位の変形労働時間制は、あらかじめ各日の労働時間を明確にしておく必要があります
会社が、任意に最初に決めた労働時間を会社の都合で変更するようなものは認められません。
よくある就業規則に、
「1ヶ月を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で1日8時間、週40時間を超えて労働させることがある」
とだけ書いて、具体的な各日、各週の労働時間を定めていない場合がありますが、これは認められません。
そもそも就業規則には、必ず、始業時刻と終業時刻を明記しなければならないので、
各日の労働時間の長さだけでなく、始業終業時刻も定めておく必要があります。

3.1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合の残業代の計算の仕方は?
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業代の計算の仕方は、
まず、1日ごとでみていきます。
1日の所定労働時間を8時間以内に設定した日に残業した場合は、8時間を超えた部分の時間が残業代が必要な時間外労働になります。下記の図で言うと、②と④がこれにあたります。
もともと8時間を超える時間を所定労働時間として設定している日については、その設定した時間を超えた部分が残業代が必要な時間外労働になります。
下記の図で言うと①と⑤がこれにあたります。
次は週ごとで確認します。
下記の図の③を見てください。6日の所定労働時間は7時間なので1時間残業しても、1日ごとでみたら法定労働時間の8時間以内なので、残業代は必要無いのですが、この週は所定労働時間は38時間で、月曜日と水曜日ですでにあわせて2時間残業しているので、金曜日の所定労働時間が終了した時点で週40時間勤務していることになります。
そのため、③は週40時間を超えた時間外労働なので残業代が必要な時間外労働に該当します。
次は月で確認します。
すでに、1日ごとと週ごとでみた時間外労働となった時間を除き、変形期間の総枠の限度時間を超えた部分が割増賃金の必要な時間外労働になります。
以下の図では、31日の月なので、この月の月間法定労働時間の限度は、先に書いたように、177.1時間です。
下記の図では、もともとの所定労働時間が171時間ですから、177.1時間までは6.1時間あります。
下記の図の①~⑤まではすでに時間外労働としてカウントしていますので、月で見た場合は、まだ6.1時間残業させても残業代は付かないことになります。
よって、下記の⑥及び⑦は、1日で見ても8時間未満なので残業代が必要な時間外労働になりません。
週でみても同様ですので、⑥およ⑦は割増賃金の必要の無い残業ということになります。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077