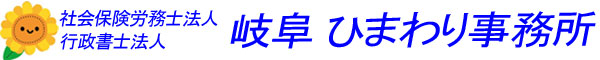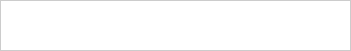派遣業を始めたい方へのサポート内容は、こちらをご覧ください。
お電話ください! 電話 (058)215-5077
派遣業顧問先事業主様からの質問
「専ら派遣」とは何ですか?
「専ら派遣」とは
いわゆる「専ら派遣」とは、
「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われる」労働者派遣事業をいいます。
例えば、派遣会社Aがあるとします。派遣会社Aが、その提携先会社Bや子会社Cだけに人材を派遣して、その他の企業へは人材を派遣しない等のケースが「専ら派遣」として挙げられます。
これは1社のみに限定して派遣する事を禁止するのみではなく、複数のグループ数社に限定して派遣する場合等ももっぱら派遣として禁止されています。
なぜ、専ら派遣は禁止なのか
なぜ、派遣会社が自社の提携先や子会社だけに限って派遣する事が禁止なのかと言うと、専ら派遣が自由に行われるようになってしまうと、企業側は本来正規雇用等で自ら雇用するべき労働者を雇用しなくなる可能性があり、外部の提携先や子会社を専用の労働供給先として扱えるようになってしまう恐れがあるからです。
ですので、正規雇用を守るための制度とも言えます。
専ら派遣に当たる判断基準
もっぱら派遣の判断基準として、以下のものに該当する場合はもっぱら派遣としてみなされる可能性があります。
① 定款等の当該事業目的が専ら派遣となっている。
② 派遣先の確保のための努力が客観的に認められない。
③ 他の事業所からの労働者派遣の依頼を、正当な理由なく全て拒否している。
上記のように、
決まった派遣先以外の会社からの派遣依頼が来た時に理由もなく断っていたり、顧客獲得のための営業活動をしていなかったり、広告宣伝活動を行わないなど、明らかに特定の企業以外との取引をする意志がないと思われる場合に、専ら派遣とみなされるのです。
ただし、この専ら派遣には例外があり、60歳以上の定年退職者を派遣労働者として雇い入れ、その割合が派遣労働者全体の3割以上である場合は専ら派遣が認められます。
顧問先事業主様からの質問
紹介予定派遣とは?
紹介予定派遣については、だいたいのことは知っているけど、細かいところはよく分からない
という方が多いように思います。
そこで、今回は、紹介予定派遣について、より詳細に解説していきたいと思います。
紹介予定派遣とは、簡単に言うと、労働者を採用したいと考えたときに、まずはお試し期間として、労働者を派遣として受け入れ、その間にその仕事ぶりや能力などを見極めたうえで、最終的に正社員として自社(派遣先)で雇用することを目的とするものです。
どの会社でも通常、「試用期間」というものがありますが、この「試用期間」の間を派遣契約という形で労働者の方には働いてもらい、試用期間(派遣期間)が終了した段階で本採用するかどうかを判断してもらうということになります。
紹介予定派遣を利用するメリット・デメリット
では、紹介予定派遣を利用するメリットは何でしょうか?
先ほども書いたように、通常、労働者を雇い入れる場合、試用期間を設けますので、特に紹介予定派遣を利用する必要はないのではないかと思われるかもしれませんが、試用期間があるといっても、採用側は、一旦、労働者を自社で直接雇用しなければなりません。
そうなると、例えば、3ヶ月間の試用期間を設けていたとしても、その間に、雇用保険・社会保険への加入義務が発生しますし、採用から14日を超えて、本採用を拒否する場合には、1ヶ月以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりませんし、解雇の正当性を問われる可能性も
あります。
紹介予定派遣であれば、保険関係は派遣元のほうで加入ですし、本採用を拒否する場合にも、その理由を伝える必要はありますが、当然、解雇予告や手当を支払う必要はありません。
ただ、当然、メリットばかりでもありません。紹介予定派遣のデメリットは、「紹介料」というコストがかかる点です。
紹介予定派遣は、有料職業紹介事業と労働者派遣事業の両方の免許を持っている業者から労働者を受け入れることになりますので、紹介予定派遣として、労働者を受け入れ、結果、本採用となった場合には、当然、業者に有料職業紹介としての紹介料を支払わなければなりません。
この紹介料は、業者によってまちまちですが、その労働者の年収のおおよそ10%から30%程度が相場のようです。
ただ、自社で募集にかけるコスト(求人広告など)等を考えると、そこまでの差はないのかもしれません。
通常の労働者派遣との違い
派遣労働者を特定することが許されている
通常の労働者派遣の場合は、派遣先が派遣労働者を特定することはできません。
例えば、派遣に先立ち履歴書を派遣元から入手するとか、事前に面接するという行為は禁じられています。
しかし、紹介予定派遣の場合は、あくまで、本採用を前提にしているので、事前面接も履歴書を事前に送ってもらうことも可能になっています。
医療関係の派遣禁止業務にも適用できる
医療機関等で行われる医療業務は、本来、派遣禁止業になっていますが、紹介予定派遣に限っては、それらの医療関連業務でも派遣が可能になっています。
派遣期間の制限
法律上で決まっているわけではありませんが、紹介予定派遣の場合は派遣元指針及び派遣先指針により、派遣期間については6ヶ月を上限とすることが求められています。
そもそも抵触日とは?
抵触日とは、ご存知の方も多いとは思いますが、派遣労働者を受け入れることができる最終日、言い換えると、これ以上派遣労働者を受け入れると派遣法違反になる日となります。
抵触日の通知は、派遣先の義務
今回の平成27年の派遣法の改正により、派遣労働者を受け入れることができる期間は3年ですが、労働組合や労働者代表の意見を聴取すれば、さらに3年の延長が可能になり、その3年経過後も再度、意見聴取すれば、何度でも延長が可能になりました。そうなると、抵触日の通知はいらないのではないかと考える方もいるようですが、そうではありません。
派遣可能期間は、あくまで3年なので、もし、最初に派遣を受け入れたのであれば、必ず派遣先は派遣元へ3年後の日付を通知しなければなりません。
そして、3年経過前に、労働組合等の意見を聴取して、さらに3年後に抵触日が変更になったのならば、その延長後の日付を遣元へ通知しなければなりません。
つまり、必ず、どのような場合でも抵触日は発生するので、それを通知しなければならないのです。
また、この抵触日の通知は派遣元ではなく、受け入れ側の派遣先が派遣元へ通知するものです
(意外と勘違いされている方がみえます)。
派遣元は、派遣先が、これまで、どのように派遣労働者を受け入れてきたか、分からないため、抵触日がいつになるか把握することができません。
そのため、あくまで派遣先が派遣元へ通知することを義務付けています。
そのため、派遣元は、派遣先から抵触日の通知が無い場合は、派遣契約を締結してはならないことになっています。

派遣契約とは
派遣契約の基本
派遣契約は、文字通り、派遣元が派遣先へ労働者を派遣し、派遣先の指揮命令下で働かせることを定めた契約です。
派遣業を行うのであれば、派遣先と必ず締結しなければならないものですが、中には何を定めるべきなのかよく分かっていない方もいるようですので、詳しく解説したいと思います。
派遣契約は、一般的には、基本的な枠組みを定めた「基本契約書」と具体的な派遣労働者の就業条件や派遣料金を定めた「個別契約書」に分けられます。
派遣法により、派遣契約には必ず定めなければならない事項が決められていますので、少なくともそれらの定めは必ず必要となります。
下記以外に当然ですが、許可または届出を行っている派遣業者から派遣を受け入れるはずなので許可番号又は届出番号の記載は必ず必要です。
派遣契約に記載しなければならない事項
必ず記載しなければならない事項は以下の内容です。
①派遣労働者が従事する業務の内容
当然ですが、派遣禁止業務を行うことはできません。
もし、1人の派遣労働者が、いくつかの業務内容の異なる仕事をする場合は、すべての業務内容を記載する必要があります。
②派遣労働者が派遣される事業所の名称及び所在地その他派遣終業の場所ならびに組織単位
一般的には「課」の単位を想定しています。そのほか電話番号など派遣元が派遣労働者に連絡できる程度の内容は必要。
③派遣先で派遣労働者に直接指揮命令する者に関する事項
具体的に指揮命令する者の部署・役職・氏名が必要
④派遣期間と働く日
期間については具体的に開始される日と終了する日
(もちろん制限期間内である必要があります)。
働く日については、具体的な曜日(例えば月曜から金曜など)等を指定。
⑤就業の開始・終了時刻と休憩時間
当然ですが、労働基準法の範囲内でかつ、派遣元と労働者との労働契約の範囲内で定める必要があります。
⑥安全・衛生に関する事項
危険有害業務に従事する場合は、その業務内容と危険又は健康障害を防止するための措置内容。
特殊健康診断が必要な場合はその実施に関する事項。
作業環境管理に関する事項。
安全衛生教育等の内容。
就業制限に関する事項。
安全衛生管理体制に関する事項など。
⑦派遣労働者からの苦情処理に関する事項
派遣労働者から苦情の申し出を受ける者の氏名・部署・役職・電話番号。苦情処理の方法等を記載。
⑧派遣契約解除に当たっての措置
派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣契約を解除する場合の事前申し入れ、派遣契約解除の予告と休業手当に関する費用負担について、解除理由の明示について等を記載
⑨派遣契約が紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣に関する事項
紹介予定派遣であること、職業紹介により従事する場合の契約内容等について記載
⑩派遣元責任者及び派遣先責任者
派遣元責任者及び派遣先責任者の役職・氏名・連絡方法等を記載
⑪時間外・休日労働をさせる場合にはその日数及び時間数
労働契約及び派遣元の36協定の範囲内で記載
⑫派遣労働者に対する福利厚生に関する便宜の供与
派遣先が派遣労働者に対し、診療所・給食施設等の施設の利用、制服の貸与、教育訓練等の便宜の供与の定めをした場合は、それを記載。
⑬その他
・事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務での派遣の場合はその旨
・産前産後休業・育児・介護休業等の代替要員としての派遣の場合は、休業する労働者の氏名、
業務内容、休業の期間
・1ヶ月の就業日数が特に少ない者の場合には、派遣先における1ヶ月の業務日数及び通常労働者の
1ヶ月の労働日数
・派遣終了後、派遣労働者を派遣先が雇用する場合の措置の内容について
・派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定するか、しないか。
派遣業を始めたい方へのサポート内容は、こちらをご覧ください。
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、派遣法改正に対応した、労働者派遣事業の許可申請はもちろんのこと、許可基準要件、資金資産要件のご説明も致します。また紹介職業許可申請も併せて行います。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077

ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金 導入サポート
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077