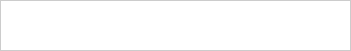労働保険と助成金
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」とがあります。
それぞれ加入要件等が定められております。
適切に労働保険に加入しないと、助成金は絶対に受給できません
よって、以下に、「労災保険」と「雇用保険」について説明しますので「労災保険」と「雇用保険」を適切に加入してください。
 お電話ください。私たちが応対します。電話 (058)215-5077
お電話ください。私たちが応対します。電話 (058)215-5077
1.労災保険
会社には、従業員が仕事中に負傷、疾病、障害、死亡した場合には、従業員や遺族の生活を補償してあげる義務があります。
と、労働基準法が定めています。
具体的には、
療養補償
療養に必要な全費用を補償する義務があります
休業補償
休業1日につき平均賃金の60%を補償する義務があります
障害補償
障害の程度に応じて平均賃金の1,340日~50日分を一時金で補償する義務があります
遺族補償
遺族に対して平均賃金の1,000日分を一時金で補償する義務があります
葬祭料
葬祭を行うものに対して平均賃金の60日分を一時金で補償する義務があります。
会社にとってこの補償を行うことは経済的に重荷になりますので、政府が管掌している保険、労災保険に加入することになります。
労災保険は、業務上や通勤途中に、労働者がけがや病気で障害が残ったり、 死亡したときに、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行います。
1.適用事業と適用労働者
労災保険は、一般の従業員はもとより、パートタイマー、アルバイト、日雇、嘱託など、その事業所で働く全ての労働者が対象となります。
このように労災保険は、労働者を使用する全ての事業に強制的に適用されます。
ただし、農林水産業の一部は、 暫定的に任意適用事業とされています。
また、本来労災保険の適用がない者の一部についても、労災保険の保護を図る「特別加入」の制度もあります。
(1) 強制適用事業
一人でも労働者を雇用して事業を行っていれば、当然に労災保険の保険関係が成立する事業をいいます。
加入・脱退の自由は認められません。
(2) 暫定任意適用事業
事業主の保険加入の申請があり、認可された場合に保険関係が成立する事業をいいます。
個人経営の 農林水産業で、使用する労働者が5人未満の事業が該当します。
(3) 特別加入
中小事業主、自営業者(個人タクシーの運転手、大工・左官)などが一定の条件を満たしたときに対象となります。
2.業務災害とは
労災保険の対象となる業務災害とは、労働者の仕事中の負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
そして、業務災害であるかどうかは、
① 労働者が労働契約に基いて事業主の支配下にある状態(業務遂行性)と、
② 業務に起因して事故等が起こり、その災害によって傷病等が発生した(業務起因性)
という2要件から判断されます。
つまり、業務、事故、傷病の間に、相当因果関係がなければ業務上の事由とは認められません。
3.通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤途中に被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の通勤とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を往復すること」をいい、その通勤が「合理的な経路 および方法」であり、「業務の性質を有するものを除く」ことになっています。
また、「逸脱・中断」があった場合には、その逸脱・中断の間とその後は通勤とは認められません。
ただし、 日用品の購入など日常生活上やむを得ない行為を、最小限の範囲で行う場合は、通常の経路に戻った後は通勤と認められます。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復が、労災保険法の 通勤の要件を満たしていることが必要となります。
4.労災保険の給付
労災保険で受けられる給付には次のようなものがありますが、業務上災害のときは「補償給付」、通勤災害の場合は 単に「給付」という名称がついています。
また、労災保険には、労働福祉事業として特別支給金の制度があり、以下の給付に上乗せされて、特別支給金が支給されるものもあります。
(1) 病気・けがをしたとき→ 療養補償給付(療養給付)
業務上災害・通勤災害により、病気やけがをしたときに、必要な医療を受けることができます。
業務上の場合は無料で、通勤災害の場合は200円の一部負担金が必要となります。
原則は、労災指定病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出して、現物給付を受けますが、指定病院が近くになかった場合は、一旦立替払いをして、払い戻しの手続をします。
(2) 病気・けがで会社を休んだとき → 休業補償給付(休業給付)
傷病の治療のため4日以上会社を休み賃金が支給されないとき、休業4日目から支給されます。
1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
この他に、20%の休業特別支給金が支給されます。
給付を受けるときは、「休業(補償)給付支給請求書」に事業主と医師の証明を受けて労働基準監督署に提出します。
(3) 病気・けがが1年6ヵ月経っても治らないとき → 傷病補償年金(傷病年金)
業務上災害・通勤災害による病気やけがが、1年6ヶ月経っても治らず、傷病の程度が傷病等級に該当するときは、休業補償給付(休業給付)に代えて年金が支給されます。
「傷病の状態等に関する届書」に医師の診断書を添えて、労働基準監督署に提出します。
(4) 傷害が残ったとき → 障害補償給付(障害給付)
① 障害補償年金(障害年金)
業務上災害・通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合は、障害の程度により、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支給されます。
② 障害補償一時金(障害一時金)
業務上災害・通勤災害による傷病が治った後に、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合は、障害の程度により、給付基礎日額の503日から56日分の一時金が支給される。
給付を受けるときは、「障害(補償)給付支給請求書」に医師の診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
(5) 死亡したとき → 遺族補償給付(遺族給付)・葬祭料(葬祭給付)
① 遺族補償年金(遺族年金)
業務災害・通勤災害により死亡したとき、遺族の数等に応じて、給付基礎日額の245日から153日分の年金が支給されます。
「遺族(補償)年金支給請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
② 遺族補償一時金(遺族一時金)
遺族(補償)年金を受けられる遺族がいないとき、年金を受けている人が失権し、他に年金を受けられる人がいない場合で、 すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、一時金が支給されます。
「遺族(補償)一時金支給請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
③ 葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行った者に315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支給されます。
「葬祭料(葬祭給付)請求書」に死亡診断書等を添えて、労働基準監督署に提出します。
(6) 介護をうけているとき → 介護補償給付(介護給付)
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の者で、現在介護を受けている者に支給されます。
自動変更対象額
補償額を算出するのに、給付基礎日額を使います。
給付基礎日額とは、原則として労働基準法12条に規定する平均賃金に相当する額とされています。
しかし、労働者によっては事情により給付基礎日額が極端に低い場合もありますので、それでは被災労働者の補償が充分にできなくなります。
そこで、補償の実効性を確保するため、給付基礎日額の最低保障額を定めることにしました。
この最低保障額を難しい言葉で自動変更対象額と言います。
この自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、変更することとされています。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助したり、定年後の再雇用育児・介護による休業などで賃金が低くなってしまった人を援助することを目的とした、国が運営する保険です。
1.適用事業
雇用保険は、労働者を雇用するすべての事業に適用されます。
ただし、農林水産業の一部については、 当分の間は、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業は任意適用とされています。
2.被保険者となる人
雇用保険の適用事業で働く労働者は、原則、その意思にかかわらず強制的に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後新たに雇用されている人、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人などは雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。
3.被保険者の種類・範囲
(1) 被保険者の種類
被保険者には次の4つの種類があります。
① 一般被保険者
適用事業に雇用される者
② 高年齢継続被保険者
同一の事業主の適用事業に65歳に達する以前から引続いて雇用されている者
③ 短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者
④ 日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者のことで、日々雇用される者または、30日以内の期間を決めて雇用される者
(2) パートタイマーの場合
パートタイマーとは、一週間の所定労働期間が、その会社の一般の労働者より短かく、かつ40時間未満である者をいいます。
次のいずれにも当てはまる場合に限り、被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 30日以上引続き雇用される見込みがあること
③ 労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則や、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
4.会社で行う各種事務
(1) 従業員を雇用したとき
従業員を雇用したときは、事業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を
提出します。
提出期限は入社した日(資格取得日)の属する月の翌月10日までです。
被保険者になったことを確認するために、労働者名簿、タイムカード等の添付書類が必要となります。
(2) 被保険者が退職したとき
被保険者が退職して被保険者でなくなったときは、退職した日の翌日から10日以内に、会社を管轄する公共職業安定所に 「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
資格喪失届を提出するときは、退職する被保険者に「離職証明書」が必要かどうかを確認してください。
5.雇用保険の給付
(1) 退職し失業状態になったとき → 求職者給付
求職者給付は、被保険者が離職し失業状態にある場合に、失業者の生活を安定させ求職活動を容易にするために支給されるものです。
① 基本手当
一般被保険者が失業し、一定の受給要件を満たした場合は、失業している日について基本手当を受給できます。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間となっていますが、その間に出産、病気などで 30日以上働くことができないときは、申請により、その日数だけ(最大3年)受給期間を延長することができます。
基本手当の日額は、離職前の賃金日額のおよそ50%~80%で、年齢別に上限額が設定されています。
給付日数は、離職理由や被保険者期間等に応じて、90日から360日の間で決まります。
② 技能習得手当
公共職業安定所の指示により職業訓練を受けたときは、その期間支給されます。
③ 寄宿舎手当
職業訓練を受けるために、同居家族と別居して寄宿する場合に支給されます。
(2) 再就職が決まったとき → 就業促進手当
離職後、公共職業安定所に失業と認定され求職の申込みをしているときに、再就職が決まり、一定の要件を満たした場合に、 支給を受けることができます。
① 再就職手当
受給資格者が常用として就職したとき
② 常用就職支度手当
45歳以上の人や障害者その他の就職困難者に該当する受給資格者が常用として就職したとき
③ 就業手当
受給資格者が「再就職手当」に該当しない、常用以外の形で就職したとき
(3) 教育訓練を受講したとき → 教育訓練給付
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または被保険者であった者(離職後1年以内)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合にはその受講料の一定の割合が支給されます。
(4) 高齢になり賃金が下がったとき → 高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者期間が5年以上ある人が、60歳時点に比べて賃金額が75%未満になった場合、 新しい賃金の15%を上限に支給されます。
高年齢雇用継続給付は、60歳以降被保険者として引き続き雇用されるときに支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当等を受給後再就職して被保険者になったときに支給される「高年齢再就職給付金」があります。
(5) 育児で休んだとき → 育児休業給付
育児休業給付は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者に給付されます。
育児休業開始前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月が12ヵ月以上あることが必要となります。
育児休業中に、休業前賃金日額の30%相当額が「育児休業基本給付金」として、職場復帰後に、休業前賃金日額の20%相当額が 「育児休業者職場復帰給付金」として、支給対象となった日数分支給されます。
(6) 介護で休んだとき → 介護休業給付
介護休業給付は、対象家族を介護するために介護休業を取得した被保険者に給付されます。
対象となる家族は、配偶者、父母、配偶者の父母、子供、被保険者と同居しかつ扶養関係にある祖父母、兄弟、孫などです。
介護休業開始前2年間に、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月が12ヵ月以上あることが必要となります。
休業前賃金日額の40%相当額が、支給対象となった日数分支給されます。
労働保険の適切な加入手続は、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、労働保険だけでなく社会保険の加入手続きもあわせて行っているだけでなく、労災保険の手続きの方法や処理も行います。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077

ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金 導入サポート
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
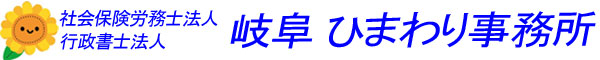

 お気軽にお問合せください。電話 (058)215-5077
お気軽にお問合せください。電話 (058)215-5077