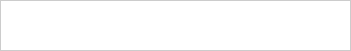社会保険と助成金
社会保険には、「健康保険」と「厚生年金保険」とがあります。
適切に社会保険に加入しなければ、助成金は絶対に受給できません
よって、以下に、「健康保険」と「厚生年金保険」について説明しますので助成金受給のために、適切に加入してください。
 お電話いただければ、私たちが応対します。電話 (058)215-5077
お電話いただければ、私たちが応対します。電話 (058)215-5077
健康保険とは
健康保険は、仕事中や通勤途中以外で、病気、けが、出産、死亡した時に、保険給付を行います。
本人だけでなく、その者に扶養されている家族も、保険給付を受けることができます。
1.健康保険の給付
健康保険では、被保険者同様、被扶養者も保険給付を受けることができます。
ただし、被扶養者は収入がないので、休業中の給与を補償する傷病手当金と出産手当金については給付がありません。
(1) 病気やけがをしたとき
① 療養の給付
健康保険証を病院の窓口に提示すれば、必要な医療を受けることができます。
70歳未満までは医療費の7割が給付され、残りの3割が自己負担となります。
② 療養費
国外で医療を受けた等、やむを得ない事情で療養の給付を受けることができなかった場合は、一旦全額を 自費で支払ったあとで、一部負担金額を除いた一定額について療養費の支給を受けることができます。
③ 高額療養費
重い病気などで長期の入院をした等、医療費の自己負担額が高額となった場合、家計の負担を軽減するために一定の金額を越えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
所得に応じて、一月ごと・同一医療機関ごとの自己負担額が、一定の限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。
④ 傷病手当金
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのため働くことができず、連続して3日以上仕事を休んでいるとき4日目から支給されます。
支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2の額となります。
支給期間は、支給を開始した日から1年6ヵ月の期間で、その間に傷病手当金を受けなかった期間があっても1年6ヵ月を過ぎたら同じ病気では傷病手当金は受けられません。
(2) 出産したとき
① 出産育児一時金
被保険者が妊娠4ヵ月(85日以降)で出産(早産・死産を含む)したときは、一児について35万円の出産育児一時金が支給されます。
② 出産手当金
被保険者が出産で仕事を休み、報酬を受けられないときは、出産の日以前42日から、出産の日の翌日以後56日目まで、休んだ期間について出産手当金が支給されます。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2の額となります。
(3) 死亡したとき
① 埋葬料
保険者が死亡したときは、埋葬を行う家族に一律5万円の埋葬料が支給されます。
② 埋葬費
家族以外の人が埋葬を行った場合は、5万円の範囲内で実費が、埋葬を行った人に埋葬費として支給されます。
(4) 退職したあとの給付
退職などで被保険者でなくなった後でも、退職前の被保険者期間、退職後の月数等一定の条件が整えば傷病手当金・出産手当金の継続給付、埋葬料・出産育児一時金の受給等が可能となります。
厚生年金保険とは
厚生年金保険は、被保険者が年をとって働けなくなったり、病気やけがで障害が残ったり、不幸にして亡くなり、 遺族が困窮した場合に保険給付を行い、被保険者とその遺族の生活を救済することを目的としています。
1.厚生年金保険の給付
厚生年金保険は、昭和61年4月の法律改正による基礎年金制の導入により、国民年金から支給される基礎年金(1階部分)の上乗せ給付(2階部分)を受け持つことに
なりました。
例えば、老齢年金については、国民年金から老齢基礎年金を、厚生年金保険からはその上乗せ給付として老齢厚生年金を支給します。
(1) 老齢になったとき
① 特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)
厚生年金保険に1年以上加入していた人が、国民年金の老齢基礎年金を受けられる受給資格期間があるときに生年月日等に応じて定められている支給開始年齢から(60歳から64歳)、65歳になるまで支給されます。
② 在職老齢年金(60歳~)
国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、在職中で厚生年金の被保険者であっても老齢厚生年金を受給できる場合があります。
しかし、給与等と年金月額の合計金額によっては、年金が一部または全部支給停止されます。
③ 老齢基礎年金(65歳~)
保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて25年以上ある人が65歳になると国民年金から支給されます。
保険料を納めた期間が長ければ長いほど(上限480月)年金額は多くなります。
④ 老齢厚生年金(65歳~)
厚生年金保険に加入していた人が、65歳になって国民年金の老齢基礎年金を受けられる受給資格期間を満たしているときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
年金額は、加入期間の長さや給料の額に応じて決まります。
(2) 障害が残ったとき
① 障害基礎年金
国民年金に加入中などの病気やけがで障害が残り、初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるときに支給されます。
障害基礎年金は1級と2級のみです。
② 障害厚生年金・障害手当金
厚生年金保険に加入中の病気やけがで障害が残り、初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるときに支給されます。
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せして受けられる1級、2級以外に障害等級3級があります。
また、障害の程度が軽いときは、障害手当金(一時金)が支給されます。
 ひまわり事務所にお問い合わせください。電話 (058)215-5077
ひまわり事務所にお問い合わせください。電話 (058)215-5077
(3) 死亡したとき
① 遺族基礎年金
国民年金加入中などに亡くなり、死亡日の前日において死亡日の前々月までに保険料を納めた期間
(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるときに、生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
遺族基礎年金が支給される子とは、18歳未満(到達年度の末日まで)、または一定の障害のある20歳未満の子を言います。
② 遺族厚生年金
厚生年金保険に加入中などの人が亡くなり、死亡日の前日において死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あるときに、生計を維持されていた妻、子、夫、父母、孫、祖父母に支給されます。
適用事業
社会保険は、事業所を単位に適用されます。
社会保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、
法律により 加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。
助成金の受給のために、適正な社会保険の加入手続は
岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい
1.強制適用事業所
常時5人以上の従業員が働いている事業所と、5人未満でも全ての法人事業所は、事業主や従業員の意思に関係なく加入しなくてはなりません。
なお、5人未満の個人事業所と、5人以上でも次の業態の事業所は、強制加入とはなりません。
2.被保険者となる人
適用事業所に使用されている人は、原則として、すべて被保険者となります。
この「使用される人」とは、実際にその事業主のもとで使用され、労働の対償として給料や賃金を受け取っている人を 言います。
事業主との間に使用関係のない、非常勤の顧問、監査役などや、個人経営の事業主は被保険者になりません。
また、パートタイム労働者の場合は、常用的使用関係にあるかどうかで判断され、所定労働時間と所定労働日数が、どちらも通常の労働者の4分の3以上である場合に被保険者となります。
例外として、被保険者とならない人は、
① 船員保険に加入している人
② 国民健康保険組合に加入している人
③ 日々雇い入れられる人
④ 2ヵ月以内の期間を定めて雇われる人
⑤ 季節的業務に4ヵ月以内の期間雇われる人
⑥ 臨時的事業に6ヵ月以内の期間雇われる人などです。
3.被扶養者となる人
健康保険では、被保険者に扶養されている家族が病気やけがをしたときにも、必要な保険給付を行います。
この保険給付が行われる扶養家族を「被扶養者」といいます。
(1) 被扶養者の範囲
被扶養者となれるのは、被保険者の三親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している次のような人です。
① 生計維持のみ
被保険者の直系尊属(父母、祖父母)、配偶者(内縁も可)、子、孫、弟妹
② 生計維持 + 同一生計(住居・家計を共にすること)
①以外の三親等内の親族
(兄、姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母・子)内縁関係にある配偶者の父母・子(配偶者の死亡後も可)
(2) 生計を維持されている人とは
① 被保険者と同一世帯の場合
② 被保険者と同一世帯でない場合
年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送額より少ない場合は、原則として被扶養者になります。
③ 60歳以上の高齢者・身体障害者の場合
年収の基準が「180万円未満」となります。この年収には、各種年金なども含まれます。
4.会社で行う各種事務
(1) 従業員を雇用したとき
被保険者になる人を採用したときは、事業主は資格取得の日から5日以内に、社会保険事務所に
「被保険者資格取得届」を提出します。
届が受理されると、事業所に「被保険者標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者証」が交付されます。
(2) 被保険者が退職したとき
従業員が退職して被保険者でなくなったときは、事業主は資格喪失の日から5日以内に、社会保険事務所に 「被保険者資格喪失届」を提出し、「健康保険被保険者証」を返却します。
資格喪失日は退職日の翌日となります。
5.社会保険料の算定・納付
(1) 標準報酬月額
健康保険や厚生年金保険では、保険料や保険給付の額を、被保険者が受ける報酬の額を基礎として算定します。
そこで、毎月の給料などの報酬を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を設定しています。
また、賞与の保険料については、上限金額を設定したうえで、「標準賞与額」に、保険料率を掛けて算出します。
【社会保険料の「賞与」の取扱いが明確化されました】は、こちらをご覧ください
(2) 標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の決め方には、次の4通りの方法があります。
① 資格取得時決定
新しく被保険者の資格を取得した従業員の標準報酬月額は、被保険者資格取得届を基礎にして決め、入社の時期によりその年または翌年8月まで有効とします。
② 定時決定
報酬は昇給などで変動するので、現在の報酬に対応した標準報酬月額とするため、全ての被保険者について、 毎年1回、標準報酬月額の見直しをします。
これを、「算定基礎届」による「定時決定」といいます。
対象となるのは、7月1日現在の被保険者で、4月、5月、6月の報酬を平均して新しい標準報酬月額を決定しその年の9月から翌年8月まで適用します。
③ 随時改定
定時決定で決まった標準報酬月額は、原則として次の定時決定まで変わりません。
しかし、大幅な昇給、降給により報酬の額が著しく変動する場合は、標準報酬月額の改定を行うことが出来ます。
これを「月額変更届」による「随時改定」といいます。
随時改定は、次の3つの条件全てに当てはまる場合に、変動があった月から4ヵ月目に行われます。
・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
・変動月以後引き続く3ヵ月間とも支払い基礎日数が17日以上あるとき
・変動月から3ヵ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じたとき
④ 育児休業等終了時の改定
被保険者が、育児休業期間を終了して、職場に復帰したときに、時間外労働をしないことなどで報酬が休業前と比べ 変動する場合があります。
このような場合、随時改定に該当しなくても「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出して終了後の3ヵ月間の 報酬月額の平均で標準報酬月額を改定することが出来ます。
(3) 報酬となるもの
標準報酬月額の算定の基礎となる「報酬」とは、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他名称を問わず労働者が 労働の対償として受けるもの全てです。
通勤手当も、社会保険では、全額報酬となります。
現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。
ただし、3ヵ月を超える期間ごとに受ける賞与は含みません。
(4) 保険料
① 健康保険
保険料は、事業主と被保険者とが折半で負担します。
事業主は、被保険者に支払う給料から被保険者負担分の保険料を引いて、事業主負担分と合わせて保険者に 納付する義務があります。
負担割合は、事業主負担分を増やすことはできますが、上限が決まっています。
② 厚生年金保険
厚生年金保険の保険料も、健康保険と同様、事業主と被保険者が折半で負担します。
○ 育児休業期間中の保険料免除
被保険者が育児休業等を取得したときは、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主・被保険者負担分共に免除されます。
事業主は、「育児休業等取得者申請書」を社会保険事務所に提出します。
事業主は、毎月の保険料を、翌月末までに納付する義務を負っています。
被保険者の当月分の給与から控除できるのは、前月分の保険料です。
事業主は、控除した前月分の保険料を、 前月分の事業主負担分と併せて、月末までに納付します。
保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月分まで、月単位で納めます。
月単位で計算するので、入社した日が1日でも、31日でも、丸々1ヵ月分が徴収されます。
また、資格を喪失した日というのは退職日の翌日なので、月末に退職した場合は、退職月の保険料が徴収されます。

社会保険のよくある質問
質問1:交通事故など第三者行為でケガをしたときは健康保険が使えますか?
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、健康保険や厚生年金保険、介護保険 国民健康保険などの医療保険、雇用保険の加入手続きはもちろんのこと、給付金額、会社負担額、社会保険制度の解説や被保険者になりうる人のご説明、年金額の計算や従業員の給与や役員の報酬の決め方をアドバイスいたします。また、労働の人事採用>方法や管理までご相談に乗ります。
適切な社会保険加入につきましては、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます
お気楽にお問い合わせください
会社設立 介護業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
TEL 058-215-5077
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金 導入サポート
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
介護事業コンサルタント
愛知で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
愛知で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
助成金申請代行 独立開業経営支援
愛知で助成金申請代行
岐阜で助成金申請代行
給与計算代行 独立開業経営支援
愛知で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
愛知で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
愛知で会社設立
岐阜で会社設立
派遣業 独立開業経営支援
愛知で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
愛知で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
愛知でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4-111 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
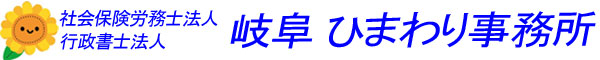

 お気軽にお問合せください。電話 (058)215-5077
お気軽にお問合せください。電話 (058)215-5077